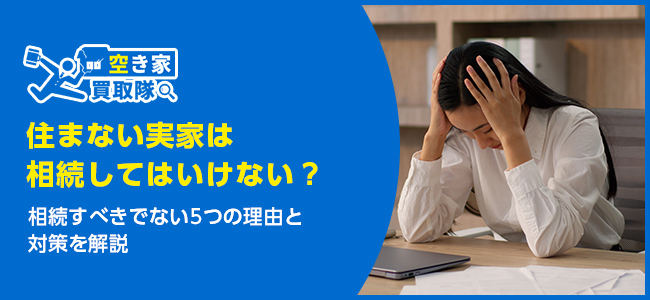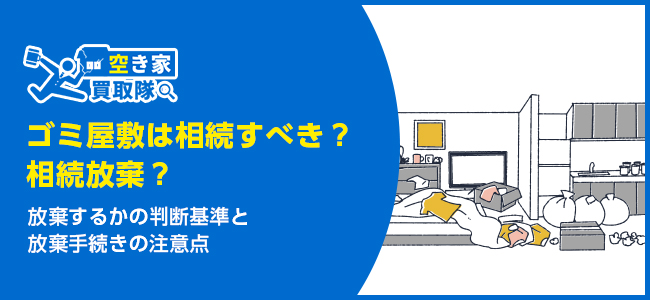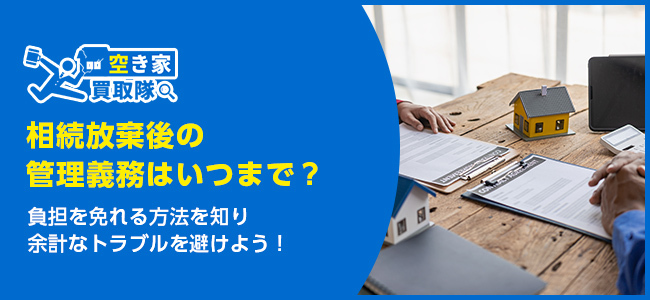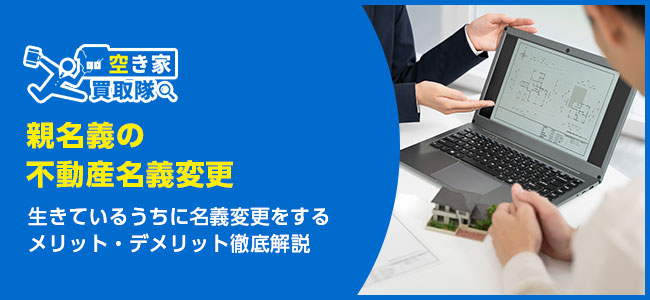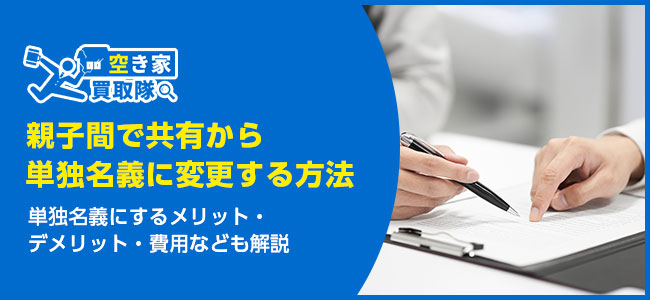そもそも、亡くなった親の家に住むことは可能?
「親が亡くなったあと、その家に住んでもいいのか?」と不安に思う方も多いでしょう。
結論として、亡くなった親の家に住むことは可能ですが、法的な手続きが必要不可欠です。
亡くなった親の不動産は「相続財産」として法定相続人に引き継がれますが、その不動産を自分の名義で正式に管理・活用するためには「相続登記」が必要です。
相続登記を行うことで、第三者に対しても自分が所有者であることを証明でき、売却や担保設定といった手続きも可能になります。
遺産分割協議が整っていない段階で一方的に住み始めると、他の相続人との間でトラブルが発生するリスクが高くなります。
また、住宅ローンの残債がある場合や建物が老朽化している場合には、補修や返済の負担も発生します。また、空き家期間中には防犯・火災リスクなどの管理責任も問われるため、「住む」という判断には慎重な検討が必要です。
感情的な想い出だけで判断せず、手続き・費用・家族間の合意形成といった要素を総合的に考える必要があります。
「住めるか」だけでなく、「どう住むか」「その準備ができているか」が重要なポイントです。
相続登記をしないまま住むとどうなる?名義変更の重要性とリスク
親の家にそのまま住み始める際、名義を変更せずに済ませようとする人もいますが、相続登記(名義変更)をせずに居住することには下記のリスクが伴います。
2024年4月から相続登記が義務化され、「相続開始を知った日から3年以内」に登記をしないと最大10万円の過料が科される制度が導入されています。
この制度改正は、所有者不明土地問題の解消、また空き家問題の解決や権利関係の明確化を目的としたものです。
また、名義が故人のままの状態が続けば、相続人同士での感情的な衝突やトラブルにも発展しかねません。たとえ現在は円満であっても、将来に禍根を残すことになります。
早めに名義変更を済ませておくことが、自分と家族の安心につながります。
登記を怠ると売却・担保設定・名義主張(第三者に対抗)ができなくなる
登記をしないままでは、法定相続人として権利は発生していても、第三者に対して自分の所有権を主張(対抗)できません。
登記を怠ると、たとえ自分が住んでいても、売却・住宅ローン・名義主張といった資産活用が一切できなくなるのです。
たとえば、その家を売却したいと考えても、登記が故人のままでは不動産会社は対応できません。
金融機関もリフォームローンを組ませてくれません。
また、名義が違うために第三者から詐欺被害にあう危険もあります。
不動産を「所有すること」と「使用すること」は別問題であると認識し、相続が発生したら速やかに登記手続きを行いましょう。
2024年から義務化!登記しないと過料の対象に
2024年4月より、相続登記の申請が義務化されました。
相続を知ってから3年以内に登記しない場合、10万円以下の過料が科されることになります。
これは全国的に問題となっている所有者不明土地問題や相続未登記による空き家や共有状態の解消を目的としたもので、市町村や法務局による調査も強化されています。
長期間放置され所有者不明土地とみなされると、所有者不明土地が社会問題となっていることから、今後、相続人に対する調査や登記申請の働きかけが強化される可能性があります。
「時間がない」「面倒そう」と感じて後回しにする人も多いですが、過料という経済的リスクを回避するためにも、登記は必ず行いましょう。
家族や他の相続人と将来トラブルに発展する可能性も
名義変更をしないまま家に住み続けると、他の相続人との感情的な対立や法的トラブルを招く恐れがあります。
「自分だけが家に住んでいる」「家賃を払っていない」などといった不公平感が、兄弟姉妹との関係を悪化させる要因になりがちです。
実際、家庭裁判所への遺産分割調停の多くが不動産をめぐる争いに起因しており、登記の放置は「争族(そうぞく)」を生む温床となります。
将来的に自分が亡くなった場合、次の世代への相続が複雑化して「負動産化」するリスクも高まります。
「今は問題ないから大丈夫」と思わず、早期に名義を整えることが賢明な判断です。
亡くなった親の家に住むために必要な相続手続きの流れ

亡くなった親の家に住むには、感情や慣れだけでなく「法的な権利」を明確にする手続きが必要です。
正しいステップを踏まなければ、不法占拠や家族間のトラブルに発展するリスクがあります。
ここでは、家を正式に自分の居住地とするために必要な「5つの相続手続き」をわかりやすく解説します。
1. 相続人の確定と財産調査
まずは「誰が相続人か」を明確にすることから始まります。
戸籍謄本や除籍謄本を取り寄せて、法定相続人を正確に確定する必要があります。
相続人に再婚相手の子や認知された子がいる場合など、見落としがちなケースにも注意が必要です。
加えて、土地・建物・預金・借金など、すべての遺産を正しく把握することも大切です。
負債も相続対象となるため、内容を曖昧にしたまま進めるのは非常に危険です。
司法書士や税理士に相談することで、トラブルの回避につながります。
2. 遺言書の有無の確認と検認
遺言書が有効な形式で存在すれば、その内容に従って相続が行われるのが原則です。ただし、遺留分などの制約がある点にも注意が必要です。
自筆証書遺言または秘密証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での「検認」手続きが必須です。
勝手に開封すると、無効やトラブルの原因になるため注意しましょう。
一方、公正証書遺言なら検認不要ですが、内容の確認と手続きは欠かせません。
「誰が家を相続するか」が明確に記載されていれば、他の相続人の同意が不要な場合もあります。
遺言の有無は、その後の協議や名義変更に大きく関わるため、早期の確認が肝心です。
3. 遺産分割協議で合意を得る
遺言書で全ての相続先が指定されていない場合、法定相続人全員での合意(遺産分割協議)が必要になります。
たとえ1人でも反対すれば、家の名義変更はできません。
協議の内容は文書化し、「遺産分割協議書」として相続人全員が、署名・押印を行います。
感情的な対立を避けるためにも、第三者である専門家の同席が効果的です。
遺産分割協議がスムーズに進まない場合、調停や審判といった法的手続きに発展する可能性もあります。
4. 相続登記の申請(名義変更)
協議が整ったら、法務局で不動産の名義変更(相続登記)を行います。
これにより、正式にその家の「所有者」になることが可能です。
申請には、戸籍・協議書・印鑑証明書などの書類が必要で、2024年からは登記が義務化され、未申請には過料が科されます。
名義を自分にすることで、売却・担保・贈与などの活用も可能になります。
住むだけでなく、所有するための必須ステップとして、確実に済ませましょう。
5. 相続税の申告と納税
最後は、相続税の申告と納税です。
申告が必要な人は「相続開始から10か月以内」に手続きを行わなければなりません。
参照元:相続税の申告と納税
評価額が高い不動産を相続する場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などを活用すれば、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。
ただし、適用には細かな条件があるため、税理士など専門家への相談が非常に重要です。
損をしないためにも、早めに財産の評価と節税対策を検討しておきましょう。
実家の処分に迷っている、話がまとまらないといった場合には、豊富な実績を持つ不動産買取業者に相談するのも一つの選択肢です。
弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。
「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。
社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
亡くなった親の家に住むメリットとデメリット
亡くなった親の家に住むことには、費用面や心理的なメリットがある一方で、維持費や家族間トラブルといったデメリットも存在します。
代表的なメリットとデメリットを3つずつ紹介し、それぞれの判断材料にしていただけるよう解説します。
亡くなった親の家に住む3つのメリット
親の家に住み続けることには多くのメリットがあります。
- 家賃不要で住める
- 心理的な安心感が得られる
- 小規模宅地等の特例など、節税特例が活用できる
それぞれの内容と注意点について解説します。
家賃不要で住める
最大のメリットは、新たに家を借りたり買ったりする必要がなく、家賃を支払わずに住めることです。
例えば都心部では月10万〜15万円の賃料が相場ですが、実家であればこのコストがゼロ。生活費全体を抑える効果があります。
老後の生活費や子育て世帯の負担軽減にもつながるため、経済的メリットは非常に大きいです。
心理的な安心感が得られる
住み慣れた土地や思い出の詰まった家に住むことは、精神的な安定や心の整理に大きく貢献します。
特に親が亡くなった直後は、環境の変化がストレスになることもありますが、実家であれば落ち着いて日常生活を再構築できるでしょう。
近所付き合いや子どもの学区が変わらない点も安心材料となります。
小規模宅地等の特例など、節税特例が活用できる
親の家に住み続けることで、相続税の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できる場合があります。
この特例により、本来数百万円かかる相続税が大幅に軽減されることもあります。
ただし、適用には同居や申告期限内の手続きなど条件があるため、税理士に相談して制度の活用可否を確認することが重要です。
亡くなった親の家に住む3つのデメリット
親の家に住むことは一見コストを抑えた選択に見えますが、実際には維持費や法的手続き、他の相続人との関係性といった課題が発生する可能性があります。
住み続けるという判断は、感情面や金銭面だけでなく、長期的な視点からも検討する必要があります。
とくに築年数が経過した住宅では修繕負担がかかるうえ、相続にまつわるトラブルも起こりがちです。
- 修繕費がかかる
- 固定資産税が発生する
- 相続人間でトラブルが起きる可能性がある
ここでは、実際に起こりやすい3つのデメリットを詳しく取り上げ、それぞれへの備えについても解説します。
修繕費がかかる
築年数が経過した家では、住み続けるために修繕や改修が必要になることが少なくありません。
屋根・外壁・水回りなどの工事には、数十万円〜100万円以上かかることもあります。
初期費用がかからない代わりに、維持費や快適性を確保するための支出が避けられない点は注意が必要です。
固定資産税が発生する
所有者になることで、毎年の固定資産税・都市計画税が発生します。
地方の一戸建てでも年間10万〜30万円程度は見込んでおく必要があります。
マンションであれば、管理費・修繕積立金などの支払いも継続的に発生し、賃貸よりも「維持する責任」が重くなります。
相続人間でトラブルが起きる可能性がある
自分だけが親の家に住む場合、他の相続人から不公平だと感じられることもあります。
「家賃を払っていない」「財産を独占している」といった不満が、遺産分割協議の場での対立に発展するケースも珍しくありません。
こうしたリスクを避けるには、事前に法的手続きを経て同意を得ておくことが大切です。弁護士や司法書士などの専門家の助言を受けながら進めると安心です。
弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。
「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。
社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
亡くなった親の家に住む前に準備できる3つのこと
親の家に将来住みたいと考えているなら、相続が発生する前の準備が非常に重要です。
遺産トラブルや複雑な手続きを未然に防ぐには、早めの対策が効果的です。
親が元気なうちから進めておきたい代表的な3つの準備について解説します。
遺言書の作成でトラブルを予防
最も有効な対策のひとつが、遺言書の作成によって相続の意思を明確にしておくことです。
「長男には自宅」「次男には預貯金」などと記載すれば、相続人間の誤解や対立を回避しやすくなります。
自筆遺言も可能ですが、法的リスクを避けたいなら公正証書遺言がおすすめです。
形式の不備が少なく、家庭裁判所での検認も不要なため、手続きもスムーズに進められます。
「言わなくてもわかる」は通用しない時代。確実に「書き残す」ことが、家族への最大の配慮になります。
生前贈与は有効だが税金や費用に注意
親が生きているうちに家を譲ってもらう「生前贈与」は、早期に名義を取得できるメリットがあります。
ただし、贈与税・登録免許税・不動産取得税などのコストが発生する点に注意が必要です。
特に贈与税は110万円を超えると課税されるため、「相続時精算課税制度」の活用がポイントです。
参照元:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
贈与はタイミングや金額の設計が重要なため、税理士など専門家と事前にシミュレーションすることをおすすめします。
共有名義を避けるなら代償分割を検討
将来親の家に住む予定があるなら、「共有名義」は避けるべきです。
共有になると、売却やリフォームのたびに全員の同意が必要となり、管理が非常に困難になります。
これを避ける方法が「代償分割」。自宅を単独相続する代わりに、他の相続人に金銭などで補填する方法です。
たとえば「長女が家を相続し、長男に500万円を渡す」などの形が代表例です。
あらかじめ金融資産や生命保険で代償金を用意しておけば、相続人間の納得と公平性を両立させることが可能になります。
弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。
「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。
社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
亡くなった親の家に住まない3つの選択肢
亡くなった親の家を相続しても、必ずしも「住む」という選択だけではありません。
ライフスタイルや経済状況に応じて、住まないという判断も現実的です。
ここでは、住まない場合に検討できる3つの具体的な選択肢を紹介します。
売却する
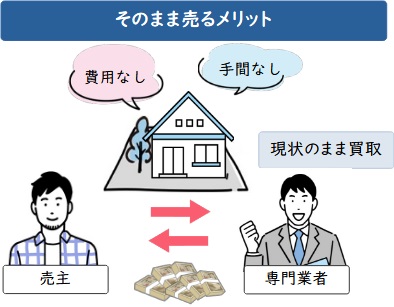
最もポピュラーな選択肢が、不動産を売却して現金化する方法です。
相続した不動産を売却する際には、まず相続登記を行い、所有権を相続人に移転する必要があります。
築年数が古かったり遠方にあったりする物件でも、売却によって維持費や固定資産税から解放されます。
相続後すぐに売却する場合、「取得費加算の特例」などの税優遇措置を利用すれば、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。
不動産会社へ相場査定を依頼し、複数の業者から見積もりを取ることが成功のカギです。
賃貸に出す
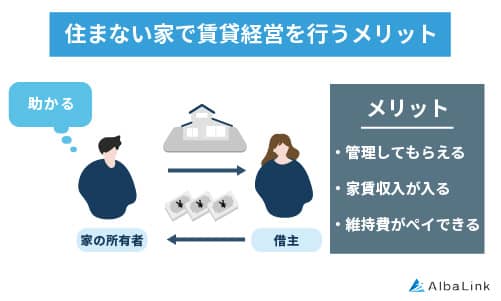
今すぐ住む予定がない、もしくは判断がつかない場合は、賃貸に出して家賃収入を得るという方法もあります。
住まずに所有し続けるメリットを維持しながら、空き家リスクを減らすことが可能です。
ただし、老朽化している物件は修繕コストや入居者確保の問題が生じる場合もあります。
また、賃貸借契約を結ぶと、将来的に自分が住みたい場合の立ち退き対応が難しいというデメリットもあります。
「賃貸活用を検討していたが、管理や修繕の手間がネックだった」と感じた場合には、手間なく現金化できる買取という選択も視野に入れてみてください。
弊社アルバリンクでは、賃貸に出すには不安が残る築古物件や訳あり物件でも、積極的に買取を行っております。
弊社アルバリンクは、売却しづらい物件の豊富な買取実績を活かし、空き家などの物件に適正な査定金額をご提示いたします。
相談・査定は弊社の無料サービスの一環なので、弊社に売却する前提でなくてもお気軽にご利用ください。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
相続放棄する
もし家が老朽化していて、維持費・修繕費・税金などの負担が大きいと判断される場合は、「相続放棄」も有効な手段です。
相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述することで、財産も債務も一切引き継がない選択が可能です。
ただし、相続放棄をすると他の財産も受け取れなくなるため、慎重な判断と事前の財産調査が必要です。
不動産が「負動産」になってしまう前に、司法書士や弁護士と相談して決断することをおすすめします。
なお、実家の相続放棄についてくわしくは、以下の記事でくわしく解説しています。

築年数が古い・住めない実家はアルバリンクに相談
親の家を相続したものの、老朽化が進んでいて住めない、売れそうにないと悩んでいる方も多いでしょう。
そんなときは、不動産買取専門の「アルバリンク」に相談するのがおすすめです。
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。
実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
まとめ|亡くなった親の家に住むには手続きと判断が重要
亡くなった親の家に住むかどうかは、感情・経済・法律・家族関係のバランスをどう取るかが問われる大きな決断です。
「住む」ためには、相続登記・名義変更・遺産分割などの手続きを正しく踏む必要があります。
住むことで得られる経済的・心理的メリットもあれば、修繕費や固定資産税、相続トラブルなどのデメリットも存在します。
また、住まないという選択肢も「売却」「賃貸」「相続放棄」と多様です。
最も重要なのは、親が元気なうちから家族で話し合いをし「どう準備するか」が、納得のいく相続と未来の安心につながります。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/