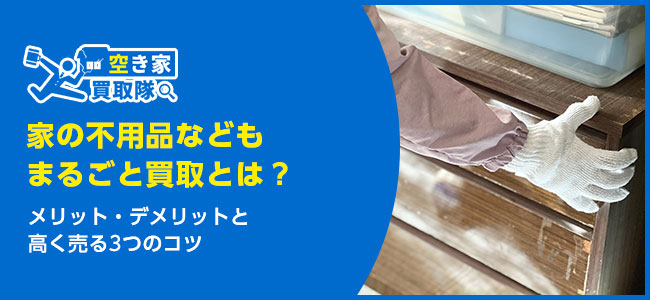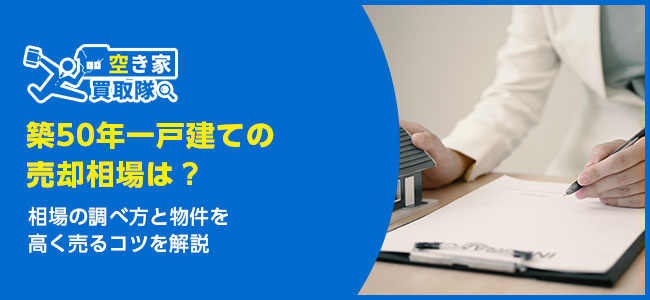土地・建物を自治体へ寄贈しても必ず引き取ってもらえるとは限らない
土地や建物を自治体へ寄付しようとしても、必ず引き取ってもらえるわけではありません。
むしろ、断られてしまうケースの方が多いのが実情です。
自治体が寄贈を断る理由には、以下のような理由が挙げられます。
- 維持管理にコストがかかる
- 固定資産税の減収につながる
それぞれの理由を確認していきましょう。
維持管理にコストがかかる
自治体が寄贈を断る理由の一つは、維持管理にコストがかかることです。
寄贈を引き受けた場合、その不動産は自治体が維持管理を引き受けます。
公共の場として利用できるものでない限りは、維持管理のコストだけが増すばかりです。
不動産の寄付を受け入れている静岡市が設けている条件の中には、維持管理コストよりも生み出される「社会的価値」「金銭的価値」が大きいことが含まれています。
自治体にとって必要性を感じない土地・建物の場合は、維持管理コストを理由に断られてしまうでしょう。
固定資産税の減収につながる
自治体が寄贈を断る理由の一つは、固定資産税の減収につながるからです。
個人が所有していれば課税できる固定資産税も、自治体が所有者となると課税できないため、税収が失われてしまいます。
自治体にとっては、使い道のない不動産の寄贈の引き受けは、維持管理コストの増加に加えて、税収減につながります。
不要な土地・建物を放置する3つのリスク
使われていない土地や空き家を長期間放置すると、所有者にとって深刻なリスクを招くことがあります。
税金・近隣との関係・行政対応など、さまざまな面で負担が重くなるため、早めの対応が求められます。
具体的なリスクは、以下の3つです。
- 固定資産税がずっとかかり続ける
- 老朽化や雑草・ゴミで近隣トラブルになる
- 行政からの指導や強制解体につながる可能性がある
放置する前に、こうしたリスクを冷静に見直し、不動産の整理や専門家への相談を検討することが大切です。
ここでは、それぞれのリスクについて確認していきましょう。
固定資産税がずっとかかり続ける
不要な土地・建物を放置するリスクの一つは、毎年の固定資産税が継続して発生することです。
所有しているだけで課税される固定資産税や都市計画税は、たとえ活用していない不動産でも免除されません。
特に利用予定のない空き家や郊外の土地では、収入がないにもかかわらず支出だけが発生する状態が続きます。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円の宅地では、年間約14万円前後の税負担が生じます(※自治体や税率により変動)。
何年も放置すれば、累計で数十万円〜百万円単位の負担となる場合もあり、経済的ダメージは看過できません。
税負担を回避するには、早い段階で寄贈・売却・相続放棄などを検討し、状況に応じて不動産を整理する必要があります。
費用や制度を把握した上で、専門家に相談しながら最適な方法を選びましょう。
老朽化や雑草・ゴミで近隣トラブルになる
不要な土地や空き家を放置すると、老朽化や雑草・ゴミの放置が原因で、近隣住民とのトラブルにつながることがあります。
総務省によると、利用目的のない空き家が385万戸と増加し、周囲への悪影響が懸念されています。
参照元:令和5年住宅・土地統計調査住宅数概数集計(速報集計)結果|総務省
例えば、景観を損なったり害虫発生が起こると、自治体や町内会への要望・苦情が寄せられるケースが多くなっています。
対策としては、以下の方法が有効です。
- 定期的な草刈りや外観の清掃を行う
- 不動産会社や専門業者に管理を委託する
- 空き家バンクに登録し、活用や売却を促進する
放置し続けることで、トラブルが長期化し、自らの労力やコストも増大します。
不要な土地・建物は、早めの対応が大切です。
行政からの指導や強制解体につながる可能性がある

不要な土地や建物を放置すると、行政からの指導や強制解体につながる可能性があります。
特に老朽化が進み、倒壊や衛生面のリスクがある物件は「空家等対策の推進に関する特別措置法」により「特定空家等」に指定され、行政指導や勧告・命令の対象となります。
命令に従わない場合には、自治体が所有者に代わって解体を実施し、その費用を請求される可能性があります。
こうしたリスクを避けるには、空き家を「放置しない」意識が欠かせません。
定期的な点検や必要な補修、あるいは早期の売却・処分を検討し、所有者としての責任を果たす姿勢が求められます。
土地・建物を自治体へ寄贈できない場合の寄贈先4選
不要な土地や建物を寄贈しようとしても、自治体に断られるケースは少なくありません。
ここでは、自治体への寄贈が難しいときに検討できる4つの寄贈先を紹介します。
- 相続土地国庫帰属制度(国への引き渡し)
- 認可地縁団体(自治会・町内会など)
- 近隣住人や知人などの個人
- 土地活用を目的とする法人
相続土地国庫帰属制度(国)
自治体への寄贈が難しい場合、国に土地を引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」を活用できます。
相続土地国庫帰属制度では、相続などで取得した土地を法務大臣の承認を得て国に引き渡すことが可能です。
ただし、建物付きの土地や境界トラブルのある土地などは対象外となるため、あらかじめ要件を満たしているかを確認する必要があります。
対象外となる土地には、以下のようなものが挙げられます。
- 建物が存在する土地
- 使用権・担保権が設定されている土地
- 境界が不明確または争いがある土地
- 土壌汚染・崖地など管理が困難な土地
制度の申請には審査手数料14,000円/1筆と、条件に応じた負担金(例:約20万円)が必要です。
申請は、対象地を管轄する法務局(本局)で受け付けています。
制度の詳細や申請書の記載方法は、法務省公式サイトや全国の法務局で案内されています。
申請に不安がある場合は、司法書士への相談も検討するとよいでしょう。
認可地縁団体(自治会・町内会)
不要な土地を地域で活用してもらいたい場合、認可地縁団体(自治会・町内会)への寄贈も一つの方法です。
地域の公益活動に役立てられるだけでなく、所有者の管理負担も軽減されます。
認可地縁団体とは、地方自治法に基づいて市町村長の認可を受けた地域団体を指し、法人格を有することで団体名義での不動産登記や契約が可能です。
防災倉庫や集会所の設置用地など、地域住民の共同活動に活用されるケースが多く見られます。
寄贈にあたっては、贈与契約書の作成や登記手続きが必要ですが、地域と良好な関係が築かれていれば、手続きが比較的スムーズに進むこともあります。
近隣住人や知人などの個人
不要な土地を手放す方法として、近隣住人や知人といった個人への寄贈も検討してみましょう。
特に隣地の所有者であれば、敷地の拡張や管理の効率化といった利点が見込めるため、関心を持たれる可能性があります。
ただし、個人への寄贈にも以下のような注意点があります。
- 贈与税や譲渡所得課税の対象となる可能性
- 所有権移転登記に必要な契約書や書類作成
- 法務局での手続き対応の必要性
上記手続きやリスクを回避するには、司法書士や税理士など専門家の支援を受けることが大切です。
信頼関係があっても、書面による合意や法的な整備を怠ると、後にトラブルとなる恐れがあります。
個人への寄贈は、場合によっては手間やコストを抑えられる手段となり得ますが、事前の条件整理をしっかりしておきましょう。
土地活用を目的とする法人
土地活用を前提とした法人への寄贈は、不要な不動産の管理負担や税負担を解消しつつ、社会的に有効活用してもらえる手段の一つです。
実際、不動産会社や再生可能エネルギー事業者、NPO法人などが受け入れ先となり、太陽光発電・シェアハウス・地域インフラ事業などに転用される場合もあります。
ただし、寄贈時には以下のような点を事前に確認しておくことが大切です。
- 寄贈先の活用目的と計画の具体性
- 契約条件や譲渡後の権利関係
- 登記や贈与契約に関する法的手続きの可否
適切な法人との連携が図れれば、資産の無駄を防ぎつつ地域貢献にもつながります。
トラブル回避のため、事前に専門家に相談し、条件整理と手続きを確実に進めましょう。
土地・建物を寄贈できないときの3つの対処法
寄贈が難しい土地や建物は、他の選択肢によって負担の軽減や資産価値の回収を図ることが可能です。
特に、譲渡先が見つからないまま所有を続けることは、固定資産税や管理費用などの面で大きな負担となります。
寄贈にこだわらず、別の観点から処分や活用を検討する必要があります。
具体的な対処法は、以下のとおりです。
- 土地や建物を活用する
- 相続放棄を検討する
- 売却を検討する
土地や建物を活用する
寄贈先が見つからない場合は、自ら活用して資産価値を見直す方法もあります。
活用によって、維持費を抑えるだけではなく、新たな収益源となる可能性もあるでしょう。
例えば以下のような活用方法があります。
- 空き家をリフォームして賃貸住宅として貸し出す
- 更地を駐車場や貸し農園として運用する
- 日照条件の良い土地に太陽光発電設備を設置し、売電収入を得る
上記のような活用により、不動産を「負債」ではなく「収益資産」に転換することが可能になります。
実行前には、不動産会社や行政の窓口、専門家に相談し、地域ニーズや初期費用、法的制限などを慎重に確認しましょう。
相続放棄を検討する

負担が大きい不動産を無理に引き継ぐより、「相続放棄」によって費用やトラブルを回避する選択肢もあります。
実際に、活用が難しい不動産の増加などを背景に、相続放棄を選ぶケースは年々増えています。
司法統計のデータを基にした調査によると、相続放棄の申述件数は、平成22年には約16万件でしたが、令和4年には約26万件にまで増加しています。
参照元:相続放棄の受理件数・利用件数は年々増加。放棄の理由の典型は?|不動産相続ガイド
相続放棄を行うには、家庭裁判所への申述が必要であり、相続開始を知った日から3ヶ月以内の期限があります。
他の相続人への影響や、放棄後の遺産分割への関わり方にも注意が必要です。
判断に迷う場合は、早い段階で弁護士や司法書士に相談し、法的なリスクを整理した上で対応しましょう。
特に、ご自身だけでなく他の相続人も放棄する可能性がある場合は、その後の不動産の行方まで理解しておく必要があります。
相続人全員が放棄した不動産が「国のもの」になるまでの流れは、以下の記事で詳しく解説しています。

売却を検討する

土地・建物を寄贈できないときは売却も検討しましょう。
売却は、管理コストや固定資産税といった負担を解消できる、現実的かつ資産価値を回収できる手段の一つです。
寄贈が難しい立地や条件の物件でも、価格設定や用途提案次第で買い手が見つかることもあります。
現金化できるだけでなく、長期にわたる管理責任からも解放されるという点で、心理的な負担も軽くなります。
ただし、売却前には以下のような点を確認しておきましょう。
- 権利関係(登記内容・共有者の有無)
- 売却価格の妥当性(査定は複数社に依頼)
- 税務処理(譲渡所得の有無・確定申告の必要性)
「どうせ売れない」とあきらめる前に、市場ニーズに合わせた売却戦略を考えてみましょう。
専門家に相談すれば、物件の魅力を引き出しながら、スムーズな売却が実現するかもしれません。
手放す前に確認したい不動産の4つのポイント
不動産を寄贈・売却・相続放棄する前に、所有物件の現状や権利関係を正確に把握しておく必要があります。
状態を見極めずに手続きを進めると、想定外の費用やトラブルにつながる可能性があります。
事前確認すべき主なポイントは、以下の4つです。
- 建物の老朽化状況・解体費用を確認する
- 境界・名義・未登記情報を整理する
- 税金や諸費用を事前に把握する
- 専門家に相談してトラブルを防ぐ
上記ポイントを押さえておくことで、不動産の適切な処分方法を見極めやすくなり、スムーズな手続きが可能になります。
それぞれのポイントを確認していきましょう。
建物の老朽化状況・解体費用を確認する
建物の老朽化状況と解体費用は、不動産を手放す際に必ず確認すべき要素です。
老朽化が進んだ建物は、安全面や維持コストのリスクだけではなく、売却・寄贈の障害となるケースも少なくありません。
特に、築年数が古く修繕履歴が乏しい物件では、以下のような課題が発生しやすくなります。
- 外壁・屋根などの破損による倒壊リスク
- 解体費用が高額になり、引き取り手が見つかりにくくなる
- 現況のままでは固定資産税の軽減措置が適用外となる可能性
活用・処分の方針を決める前に、不動産業者や建築会社に調査を依頼し、建物の状態を数値で把握しておきましょう。
状態によっては、先に解体して更地にしておくことで、買い手が見つかりやすくなるケースもあります。
境界・名義・未登記情報を整理する
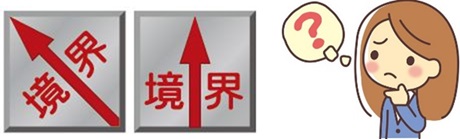
土地や建物を手放す前には、境界・名義・未登記情報といった権利関係の整理が必要です。
これらの情報が曖昧なままでは、いざ寄付や売却を進めようとしても、法的な手続きの段階で頓挫してしまうからです。
例えば、以下のような具体的なトラブルや停滞が考えられます。
| 境界が不明確な場合 | 隣地の所有者から「越境している」と主張され、所有権の範囲をめぐる紛争に発展する |
|---|---|
| 名義が故人のままの場合 | 相続人全員の同意と印鑑証明がなければ、所有権移転登記ができない |
| 建物が未登記の場合 | 法的に存在しない建物を売買・寄付はできない |
上記のような事態を避けるため、事前に権利関係を明確にしておく必要があります。
特に、相続人の調査や境界確定の測量には数ヶ月単位の時間がかかることも珍しくありません。
いざという時に慌てないよう、不明な点は専門家へ相談し早めに対応しておきましょう。
税金や諸費用を事前に把握する
不動産を手放す前には、税金や各種手数料などの費用を把握しておきましょう。
譲渡や相続の方法にかかわらず、税金が発生するケースは多く、事前に把握していないと想定外の出費につながる可能性があります。
特に譲渡所得税や登録免許税などは、数万円〜数十万円規模になることもあります。
以下のような費用項目を手放す前に確認しておきましょう。
- 固定資産税・都市計画税の年額と精算方法
- 売却時の譲渡所得税・住民税の有無と概算額
- 所有権移転登記に必要な登録免許税・司法書士報酬
- 相続登記にかかる費用や、相続税の課税対象の有無
無償で譲渡する場合でも、税金や登記費用はかかる可能性があります。
不動産会社や国税庁が提供する試算ツールを活用し、事前に金額を確認しておきましょう。
専門家に相談してトラブルを防ぐ

不動産を手放す際は、早い段階で専門家に相談すれば、想定外のトラブルを未然に防げます。
相続・寄贈・売却などの手続きは複雑で、登記や税務の知識が必要となる場面も多く、自己判断では思わぬリスクを招くことがあります。
相談先としては、以下のような専門機関を活用しましょう。
- 所有権や登記の確認|司法書士・土地家屋調査士
- 税務処理や費用の試算|税理士・会計士
- 売却や利活用の提案|不動産会社・地域の空き家バンク
近年は法テラスや自治体の無料相談窓口も充実しており、費用負担を抑えながら適切なアドバイスを得ることが可能です。
専門家のサポートを受けられれば、法的手続きの不備や後の損害賠償リスクを避け、安心して手続きが進められます。
売れない建物・土地の処分にお悩みならアルバリンクへご相談ください
「どうせ価値がない」と思って土地や建物を寄贈しようと考えている方にこそ、一度、買取業者への査定をおすすめします。
実は、市場では思わぬニーズがあり、専門業者なら「売れない」とされる不動産でも引き取り先が見つかることがあるからです。
寄贈には登記や契約、条件確認などの手間がかかる上、必ずしも受け取ってもらえるとは限りません。
一方、買取業者に依頼すれば、必要書類のサポートから引渡しまでスムーズに対応してもらえ、時間や手間を大きく削減できます。
「売れない」と思い込む前に、まずはアルバリンクなどの専門業者に査定を依頼してみてください。
意外な価値が見つかる可能性があります。
査定は無料でご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。
実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
まとめ
不要な土地や建物を「自治体へ寄贈すれば解決できる」と考える方は少なくありませんが、必ずしも引き取ってもらえるとは限りません。
自治体には維持管理のコストや利活用の難しさといった理由があり、寄贈を断られるケースも多くあります。
こうした物件を放置しておくと、固定資産税の負担や近隣トラブル、行政からの指導など、さらなるリスクを招く可能性があります。
リスク回避のためには、売却も一つの選択肢です。
特に、専門の買取業者に依頼すれば、自治体や個人では敬遠されがちな老朽化物件や使い道の限られた土地であっても、スムーズに引き取ってもらえる可能性が高まります。
アルバリンクはこうした売却困難な土地・建物の買取を数多く手がけており、全国対応・スピード対応でご相談にも丁寧に応じています。
土地や建物の処分にお悩みの方は、ぜひ一度アルバリンクへご相談ください。
きっと最適な解決策が見つかるはずです。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
電話相談も受付中!10時~19時【無料】0120-672-343