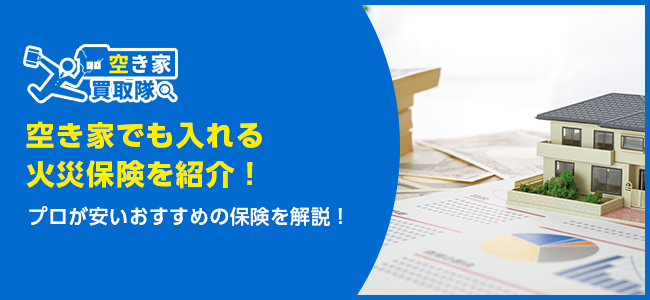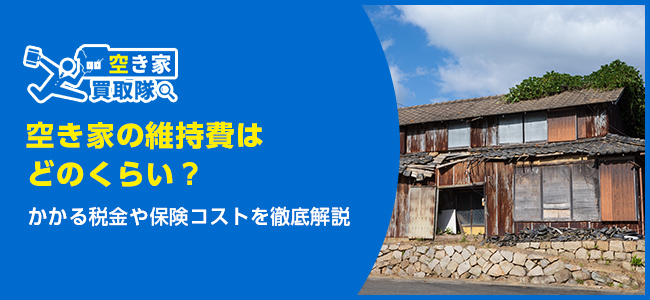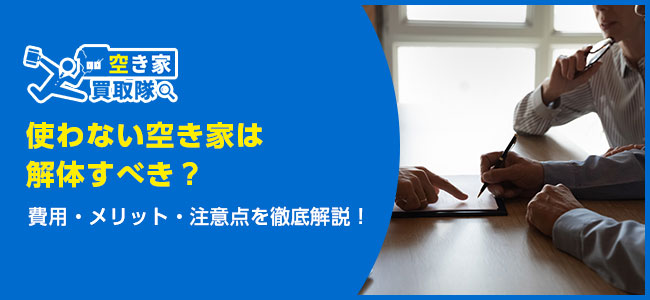空き家を解体する前に必要な手続き

空き家を解体するには、事前に複数の手続きが必要です。
怠ると、解体工事がスムーズに進まないばかりか、法的なトラブルを招く可能性もあります。
解体には「解体工事届出」や「登記の抹消申請」など、さまざまな手続きが関係しており、それぞれに提出期限や提出先が定められているため注意しましょう。
また、工事に伴う費用の相場や助成金の有無も確認しておくべきポイントです。
準備には時間も手間もかかりますが、計画的に進めることで余計な費用やトラブルを回避できます。
まずは、空き家の所有者として必要な以下の手続きの流れを理解し、事前準備を徹底しましょう。
なお、手続き以外で空き家解体前にやるべきことについては、以下の記事でくわしく解説しています。

解体工事届出の提出
解体工事を行うには、一定の条件を満たす建物について「解体工事届出」の提出が必要です。
建築基準法第15条第1項:建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
特に、住宅や空き家を含む建築物で一定規模を超えるものは、法令により事前に届け出をする義務があります。この手続きを怠ると、罰則が科されることもあるため注意が必要です。
参照元:国土交通省|建築関係法の概要
また、届出には構造や建築年などの詳細な情報を記載し、適切な書類を添付する必要があります。
多くの場合、解体業者が代行してくれることもありますが、自身でも内容を把握しておくと安心です。
手続きを確実に行い、解体作業をスムーズに開始できるようにしておきましょう。
建設リサイクル法に基づく届け出
建物の解体に際して、「建設リサイクル法」に基づく届け出が必要となるケースがあります。
延べ床面積80㎡以上の建物を解体する場合に適用され、建設資材の分別解体と再資源化を促進するための法律です。
木造や鉄骨造など、建物の構造によっても対応が異なるため、事前の調査と確認が求められます。
届け出は、解体工事の7日前までに市区町村の窓口に提出しなければなりません。
提出には建築物の図面や写真、工事の工程表などの書類が必要です。
建設リサイクル法への理解を深め、適正な処分と環境への配慮を実現するためにも、届出は確実に行いましょう。
提出先と提出期限
解体工事の届出を行う際には、提出先と期限に注意が必要です。
届け出の提出先は、原則として建物の所在地を管轄する市区町村の役所です。
都市によっては、建設課や建築指導課といった特定の部署が窓口となります。
また、届け出の提出期限は「工事開始の7日前まで」と定められており、期限を過ぎると手続きが受理されない可能性があります。
役所の受付時間は平日のみであることが多く、郵送やオンライン申請が可能な自治体もあるため、事前に確認しておくと安心です。
余裕を持って手続きを進めることで、解体工事のスケジュールにも余裕が生まれます。
確実に届け出を完了させ、トラブルを防ぎながら解体工事を進めていきましょう。
道路使用・占用許可申請
空き家を解体する際、建物が公道に面している場合には「道路使用許可」および「道路占用許可」の申請が必要です。
解体工事中に重機を道路上に設置したり、廃材を一時的に仮置きしたりする場合には、通行人や車両の安全を確保するため、道路の一部を使用または占用することになります。
手続きを怠ると違法とみなされ、工事の中断や罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。
業者任せにせず、所有者自身も手順や条件を把握し、スムーズな作業環境を整えましょう。
事前に必要な許可申請を済ませ、安全でトラブルのない解体工事を進めてください。
どこに申請するのか
道路使用・占用の許可申請は、解体を行う「現地の管轄警察署」と「市区町村の役所」にそれぞれ提出します。
道路使用許可は警察署、道路占用許可は市区町村の担当課(通常は道路管理課や土木課)になります。
- 道路使用許可:警察署
- 道路占用許可:市区町村の担当課
申請者は工事業者が行うケースが多いですが、個人で申請する場合もあります。
申請書類には、工事の内容や使用する道路の位置図、現場写真、交通整理計画図などが必要となるため、準備には時間と手間がかかります。
提出は通常、平日の窓口対応時間内に限られるため、早めの対応が重要です。
まずは解体する空き家の所在地の役所と警察署へ連絡し、必要な書類と流れを確認しておきましょう。
工事に必要な範囲・条件
道路使用・占用許可が必要となる条件は、工事の範囲や使用方法によって異なるため確認しておきましょう。
たとえば、重機を一時的に道路に設置する場合や、廃材や建材を搬出入する際にトラックが道路上に駐車する必要がある場合などが該当します。
道路の幅や周辺の交通量、近隣住民への影響なども考慮され、申請が通らないケースもあるため注意してください。
また、夜間作業や長期間の占用は特に厳しい条件が課されることも。
許可が得られた場合でも、表示板の設置や交通誘導員の配置など、安全対策を実施しなければなりません。
こうした条件を正しく理解し、事前に自治体や業者と相談しながら最適な対応を検討することが重要です。
安心・安全な工事を実現するためにも、許可の取得は早めに行いましょう。
ライフラインの停止
空き家の解体前には、ライフライン(電気・ガス・水道・通信)の停止手続きを必ず行う必要があります。
これを怠ると、作業中に漏電やガス漏れ、水漏れなどの事故が発生する危険があるほか、不要な請求が続く可能性もあります。
工事業者に依頼するだけでは完了しないケースもあるため、所有者自身で各契約会社へ連絡・解約を行うことが重要です。
停止手続きは無料で対応してくれることが多く、電話やオンラインで完了する場合もあります。
ただし、地域や契約状況により異なるため注意が必要です。
解体を安全かつスムーズに進めるためにも、ライフラインの停止は事前準備の一環として早めに対応しましょう。
電気・ガス・水道・通信の解約
空き家のライフライン停止では、まず電気・ガス・水道・通信(インターネットや固定電話など)の各契約を解約する手続きが必要です。
建物の構造や状況に関係なく継続して請求が発生することがあり、解体予定の家屋では不要な費用となります。
解約の際は、契約者本人が手続きを行うことが原則で、委任状が必要になるケースもあるため確認しておきましょう。
申請には住所や契約番号などの情報が求められるため、事前に必要書類を準備しておくとスムーズです。
解約後は「使用停止証明書」などを発行してもらえる場合もあり、滅失登記の際の証明書類として活用できることもあります。
手続きの流れを確認し、各社への連絡を計画的に進めましょう。
停止のタイミングと注意点
ライフラインの停止は、解体工事が始まる数日前~1週間前を目安に行うのが一般的です。
早すぎると現地調査や作業準備に支障をきたし、遅すぎると安全管理に問題が生じる恐れがあります。
特にガスの閉栓作業は立ち会いが必要な場合もあり、業者との日程調整に時間がかかるケースもあるため注意しましょう。
また、水道は完全に止めるのではなく「工事用仮設水道」として残すケースもあるため、業者との相談が必要です。
さらに、解体終了後にも使用停止の連絡を怠ると、後から固定資産税の請求や廃材処理に関するトラブルが発生する可能性があります。
事前に各契約会社と解約スケジュールを確認し、工事の流れに沿った適切なタイミングで停止手続きを行いましょう。
近隣への説明会の実施
空き家の解体工事を円滑に進めるためには、近隣住民への説明会の実施が非常に重要です。
重機の稼働音や振動、粉じんの発生など、解体作業には周辺環境に影響を及ぼす要素が多く含まれています。
事前に説明せずに着工すると、クレームやトラブルが発生し、作業の中断や工程の遅延に繋がる恐れがある点に留意しておきましょう。
説明会の開催は法的義務ではありませんが、所有者や依頼主の責任として「安心できる工事」を提供する姿勢が求められます。
結果的に近隣との信頼関係を築き、スムーズな撤去・更地化へと繋がるため、準備段階で説明会を計画するといった事前対応を徹底しましょう。
説明すべき内容と伝えるべきタイミング
説明会で伝えるべき主な内容には、以下のような項目があります。
- 工事の開始・終了時期
- 作業時間
- 使用する重機の種類
- 騒音や粉じん対策
- 道路の一時使用の有無
上記の情報を共有することで、近隣住民も安心して日常生活を送ることができます。
タイミングとしては、着工の1〜2週間前が理想的です。
説明会は個別訪問や書面による通知でも代用可能ですが、可能であれば直接対面での説明が誤解を防ぎやすいです。
また、自治体によっては説明の実施を推奨しているケースもあるため、事前に役所や業者と相談して進めると良いでしょう。
伝える内容をまとめた資料を作成しておくことで、よりスムーズな説明が可能になります。
トラブルを防ぐためのポイント
トラブル防止には、誠実な対応と丁寧な説明がカギとなります。
例えば、騒音や粉じんなどの環境的負荷は避けられないものの、事前に「どのような対策を講じているか」「どの時間帯に作業を行うか」などを明確に説明することで、住民の理解を得やすくなります。
また、工事中に万が一の事故や損害が発生した場合の連絡先や対応フローを提示しておくことも重要です。
さらに、作業完了後の清掃や不用品の処分対応なども、近隣への印象を左右するポイントです。
問題が発生してから慌てるのではなく、問題の「予防」ができる段階で手を打つことが、近隣トラブルを防ぎ、結果的に工事全体の負担軽減にも繋がります。
アスベスト調査と届出
空き家を解体する際には、アスベスト(石綿)に関する事前調査と届け出が必要です。
アスベストはかつて断熱性や耐火性に優れた建材として広く使用されました。
ただし、現在では健康被害が問題視され、法令で厳しく規制されています。
2006年以前に建てられた住宅や建物では、アスベストが使用されている可能性があるため、解体工事前に必ず専門業者による調査を行う義務があります。
参照元:厚生労働省
その結果に応じて、届出や除去作業が必要となり、適切に対応しなければ行政からの指導や工事中断といった問題が発生する恐れもあります。
空き家の解体を円滑に進めるためには、事前にアスベストの有無を把握し、確実な手続きを行いましょう。
特定粉じん排出等作業の実施の届出とは
アスベスト調査の結果、該当する建材が使用されていた場合、「特定粉じん排出等作業の実施の届出」が必要です。
作業によってアスベストを含む粉じんが大気中に飛散することを防ぐための届け出で、作業開始の14日前までに市区町村や都道府県の窓口へ提出します。
法律で義務付けられており、怠ると罰則が科される可能性があるため注意してください。
参照元:環境局|《大気汚染防止法・環境確保条例》特定粉じん排出等作業(アスベスト)に係る届出等
提出書類には、作業計画、現地の写真、建物の構造図などが必要であり、作成には専門知識が求められます。
通常は解体業者やアスベスト処理専門業者が対応しますが、所有者も手続きの流れや条件を理解しておくことで、安心して依頼ができます。
アスベストがある場合の対応
調査の結果、アスベスト含有建材が発見された場合は、専門業者による除去・処分作業を行う必要があります。
アスベストの処理は、通常の解体よりも手間・費用・時間がかかるため、事前に見積もりを取得しておくと安心です。
また、自治体によってはアスベスト除去に関する補助金制度を設けているケースもあるため、事前に確認しておくと費用負担を軽減できるでしょう。
作業時は近隣への粉じん飛散を防ぐための囲い込み、湿潤化、廃材の密閉搬出など、厳格な安全対策が義務付けられています。
適切な業者を選び、安全・確実な処理を行うことが健康と環境を守る第一歩です。
アスベストは見た目では判断できないため、必ずプロによる調査と対応を行いましょう。
残置物の処分
空き家の解体を行う前に、建物内に残された家具・家電・生活ゴミなどの「残置物」を処分することが必要不可欠です。
残留物があると解体作業が進められず、工事の遅延や費用の増加につながる可能性があります。
残置物の撤去は、所有者や相続人の責任で行う必要があり、専門の不用品回収業者に依頼するか、自身で自治体のルールに従って処理しなければなりません。
特に大量の残置物がある場合は、見積もりやスケジュール調整にも手間がかかるため、解体準備の段階から早めに対応しておくことが大切です。
不要物の処分は、工事の安全性や周辺環境への配慮にもつながる重要な作業ですので計画的に進めましょう。
空き家の残置物については、下記の記事でも詳しく解説しています。

家具・家電・ゴミの処理
空き家に残された家具や家電、生活用品の処理は、その種類や状態に応じた方法で適切に分別・廃棄する必要があります。
リサイクル家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど)は、家電リサイクル法に基づき、販売店や指定引取場所への搬入しましょう。
参照元:経済産業省
ベッドやソファなどの大型家具は、自治体の粗大ゴミ回収を利用するか、専門業者への依頼が一般的です。
また、生活ゴミや雑誌・衣類などの可燃・不燃物も、自治体の分別ルールに従って処分する必要があります。
不用品処分には費用もかかるため、一括処分か個別対応かを比較検討して、自身に合った方法を選ぶことがコスト削減のポイントです。
いずれにしても、建物の中を空にしなければ解体作業に進めないため、早めの対応を心がけましょう。
自治体のルールに従った廃棄方法
残置物を処分する際は、必ず各自治体の廃棄ルールを確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。
例えば、粗大ゴミの出し方ひとつとっても、「事前予約制」や「有料シールの購入」が必要な地域があり、無断で出した場合には不法投棄とみなされる可能性もあります。
また、自治体によっては「空き家対策事業」の一環として、不用品の回収や処分費用に対する助成金や補助制度を設けている場合もあります。市区町村の公式サイトや窓口で確認しておきましょう、
加えて、廃棄が難しい建材や家電については、許可を持つ業者に依頼することが安全かつ確実です。
処分方法を誤ると、解体スケジュールにも影響を与えるため、ルールに則った適正な対応を徹底しましょう。
弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。 「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。 社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。 \(無料)東証上場企業に相談・査定/
空き家を解体した後に必要な手続き

空き家の解体工事が完了した後には、「建物滅失登記(めっしつとうき)」の手続きを行う必要があります。
下記のステップで、スムーズな土地活用や売却に準備しましょう。
建物滅失登記の申請
建物滅失登記の申請は、解体後の最終的な手続きとして必要不可欠です。
法務局の登記簿から建物の記録が正式に削除され、土地が「更地」として扱われるようになります。
申請は原則として建物の所有者本人が行うものですが、委任状を用いて司法書士や土地家屋調査士に依頼するケースが一般的です。
申請には、以下の書類が必要となります。
- 建物滅失証明書(解体業者が発行)
- 登記事項証明書・申請書
- 印鑑証明書・住民票など
法務局の窓口での手続きのほか、オンライン申請に対応している場合もあります。
時間や手間がかかる作業であるため、事前に必要書類や流れを整理し、スムーズに申請を完了させることが大切です。
滅失登記とは何か
滅失登記とは、解体によって存在しなくなった建物を登記簿から抹消するための手続きです。
土地に関する登記は、不動産取引や相続の場面で正確な情報が求められます。建物がすでに存在しないにもかかわらず登記上は「存在する」となっている状況はトラブルの元になるため注意が必要です。
また、滅失登記を行うことで、固定資産税の対象から建物が除外されるメリットもあり、余計な税金の負担を軽減できます。
申請期限は法的に「解体完了から1か月以内」とされており、正当な理由なく遅延した場合、行政から指導や督促を受けるケースもあります。
所有者としての義務を果たし、土地を適切に管理するためにも、必ず滅失登記を実施しましょう。
申請に必要な書類一覧
建物滅失登記の申請を行うには、複数の書類を事前に準備しておく必要があります。主な必要書類は以下の通りです。
- 登記申請書(法務局指定の様式)
- 建物滅失証明書(解体を担当した業者が発行)
- 所有者の住民票または住所証明書(登記上の住所と異なる場合)
- 所有者の印鑑証明書(委任状を用いる場合に必要)
- 解体前の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 解体工事中や完了後の写真
- 固定資産評価証明書(税務上必要なケースも)
所有者本人が取得できるものもあれば、土地家屋調査士や司法書士などの専門家に依頼して準備するケースもあります。
不備があると手続きが遅れる可能性があるため、提出前にしっかり確認しましょう。申請にかかる手間と時間を最小限に抑えるには、事前準備を万全にしておくことが大切です。
申請手順(法務局・オンライン・代行)
建物滅失登記の申請方法には、法務局窓口での申請、オンライン申請、専門家への代行依頼の3つの方法があります。
① 法務局窓口での申請
申請者本人が書類を揃え、建物の所在地を管轄する法務局の登記窓口に直接提出する方法です。
平日の受付時間内に限られ、事前に電話で予約が必要なこともあります。
初めての方は、事前に書類の確認や登記相談を受けておくと安心です。
② オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)
登記手続きは、オンラインでも申請が可能です。
電子証明書を取得し、申請書や添付書類をPDF形式でアップロードする形で行います。
オンラインなら時間や場所に縛られず申請でき、法務局の混雑を避けられるというメリットがありますが、操作や準備に不安がある方にはややハードルが高い方法です。
③ 土地家屋調査士・司法書士への代行依頼
時間や手間をかけたくない場合は、専門家への依頼がおすすめです。
費用は発生しますが、書類作成や提出、法務局とのやり取りまで一括で任せられるため、安心して滅失登記を進められます。
費用相場は3万円~6万円ほどで、物件や地域によって異なるため確認しておきましょう。
申請方法の選択は、自身のスケジュールや知識、予算に応じて決めることが重要です。
どの方法を選ぶ場合も、提出期限(解体から1か月以内)を守ることが最大のポイントとなります。
参照元:相続会議
水道の停止と清算
空き家を解体した後には、水道の停止と料金の清算を必ず行う必要があります。
工事中に仮設水道として一時的に水道を使用していたケースや、建物に元々残っていた水道契約が継続している場合は、無駄な基本料金が請求され続ける可能性があります。
また、滅失登記の手続きや不動産の売却時に、ライフライン契約が残っているとトラブルの原因になることも。
水道は市区町村ごとに手続き方法が異なるため、早めの確認と対応が重要です。
解体工事が完了した段階で水道局へ連絡し、使用停止と清算の申請を行いましょう。
工事中に使用した水道の停止
解体工事では、粉じん対策や清掃作業のために仮設水道が使用されることが一般的です。
この水道の契約は通常、所有者または業者が市区町村の水道課に対して申し込み、工事用として一時的に開栓されます。工事が終了したら速やかに停止手続きが必要です。
水道停止の際には、「停止届」の提出が求められます。停止希望日の数日前までに連絡を入れておきましょう。
手続きは電話やオンライン、または窓口で対応している自治体が多く、現地でのメーター確認や立ち会いを求められるケースもあります。
停止忘れによる請求トラブルを防ぐためにも、解体業者とも連携し、確実な対応を心がけることが大切です。
料金精算と手続き方法
水道料金の精算は、最後の使用日をもとに日割りで計算され、後日請求されるのが一般的です。
精算方法は自治体や契約状況によって異なりますが、口座振替・コンビニ払い・クレジット払いなどが選択可能です。
水道局からの請求書が届く前にメーターの最終確認を済ませておくと、正確な金額での精算が可能になります。
また、名義変更や相続登記などの不動産関連手続きが同時進行している場合には、水道契約の名義も確認しておくことが重要です。
必要に応じて、委任状を用意しておきましょう。
解体工事の完了から遅くとも数日以内には清算手続きを済ませ、ライフラインをきちんと終了させるまでが所有者の責任です。
土地滅失登記や家屋滅失届の検討
空き家の解体が完了した後は、「建物の滅失登記」だけでなく、未登記家屋の届出や土地の状況確認なども検討が必要です。
特に、登記されていない家屋の場合、「家屋滅失届」を自治体に提出する必要があります。
手続きを怠ると固定資産税の誤課税や、不動産売却時のトラブルの原因になる可能性があるため注意が必要です。
また、古い木造建築などでは、建物が登記簿に載っていないケースもあり、こうした場合は事前の調査と適切な対応が求められます。
解体工事完了後の手続きを怠らず、土地と建物の権利関係を正確に整理しておき、将来的な資産管理や売却時のトラブルを防ぎましょう。
未登記家屋の場合の対応
未登記の家屋を解体した場合、通常の法務局への建物滅失登記ではなく、「家屋滅失届」を市区町村に提出する必要があります。
不動産課税台帳上に登録されている家屋を削除するためのもので、提出しないまま放置すると、建物が存在しないにも関わらず固定資産税が請求され続ける可能性があります。
届出には、解体業者が発行する「取り壊し証明書」や「工事完了報告書」、所有者の身分証、印鑑、固定資産税通知書などの書類が必要です。
また、提出のタイミングは解体完了後すぐ(一般的には30日以内)とされているため、解体後の早い段階で手続きを行うことが推奨されます。
具体的な期限は自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくと安心です。
手続きを怠ることで無駄な税金負担が発生するリスクがあるため、必ず対応しましょう。
法的義務と罰則の可能性
建物の滅失に伴う登記や届出には、法的な義務が伴います。
たとえば、登記簿上に登録されている建物については、解体から1か月以内に「建物滅失登記」を行うことが不動産登記法第57条で義務付けられています。
怠った場合、罰則として10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、家屋滅失届の未提出によって固定資産税の課税が続いていた場合、後になっても過払い分の還付手続きが必要となるなど、余計な手間と時間がかかるケースも。
土地の管理責任を果たすという観点からも、解体後の法的手続きは速やかに、確実に完了させることが求められます。
不明点がある場合は、法務局や市区町村の窓口、または司法書士・土地家屋調査士といった専門家に相談しましょう。
相続した空き家を解体する際の手続き

相続した空き家を解体するには、まず建物の名義や登記情報を正確に確認することが出発点です。
名義が被相続人(亡くなった親など)のままになっている状態では、解体工事や登記手続き、補助金申請などの各種対応ができない場合が多く、後々のトラブルの原因にもなります。
相続登記が完了していない空き家は、手続き全体がストップする可能性もあるため注意が必要です。
また、解体には費用がかかるだけでなく、固定資産税や法務局での登記手続き、家屋滅失登記の申請なども発生します。
スムーズに手続きを進めるためには、まず名義の確認と登記状況の調査から始めましょう。
建物の名義・登記情報の確認
相続によって取得した空き家を解体するには、建物が誰の名義で登記されているのかを明らかにする必要があります。
所有者情報が古いまま放置されているケースが少なくなく、相続登記が未了の状態では、工事の依頼や申請がスムーズに進まないため注意が必要です。
相続人が複数いる場合、登記簿に記載されている所有者が誰であるかによって、手続きの流れや対応が大きく変わる点にも留意しておきましょう。
また、登記簿を確認することで、抵当権の設定があるかどうかや、土地と建物の所有者が一致しているかといった重要な情報も把握できます。
空き家の相続に関しては、下記の記事でも解説しますので参考にしてください。

法務局での登記簿謄本確認方法
登記情報の確認は、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得することで可能です。
建物や土地の所在地が分かれば、誰でも取得でき、所有者の名前、住所、構造、築年数、抵当権の有無などが記載されています。
取得方法には、下記のは3つがあります。
- 法務局の窓口で直接申請
- 郵送による請求
- 法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用したオンライン請求
手数料は1通あたり600円〜700円前後(オンラインなら安価)で、印鑑証明書や住民票などは不要です。
相続人自身が行うこともできますし、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
正確な情報を早めに取得し、必要な手続きに備えておくことが解体後の流れをスムーズにする第一歩です。
抵当権の有無を確認する
空き家を解体する前には、建物や土地に「抵当権」が設定されていないかを確認することが重要です。
抵当権とは、金融機関が住宅ローンなどの貸付金を担保するために設定する権利で、登記簿上に記載されています。
もし抵当権が残っている状態で無断で解体を行った場合、金融機関との契約違反となり、損害賠償請求や法的トラブルに発展する可能性があり注意しなければなりません。
建物の登記情報を法務局で確認し、「抵当権抹消登記」が済んでいるかどうかをチェックすることが、事前準備として必須です。
安全かつ合法的に解体を進めるためにも、抵当権の存在を見落とさないようにしましょう。
金融機関の確認ポイント
抵当権が登記簿に残っていた場合、まずは設定している金融機関に直接確認の連絡を入れる必要があります。
その際、以下のようなポイントを事前に整理しておくとスムーズです。
- 抵当権の設定状況(ローン残債の有無)
- 解体を行う理由とスケジュール
- 担保解除や抵当権抹消の手続きに必要な書類・費用
- 解体後の土地活用予定(売却・建替えなど)
金融機関によっては、解体の前にローン完済や担保変更が求められることもあります。
また、抵当権の抹消登記には「登記申請書」や「登記原因証明情報」などの書類が必要で、司法書士への依頼が一般的です。
費用相場は数万円程度ですが、物件や条件によって異なるため事前に見積もりを取りましょう。
建物の解体は資産価値に大きく影響するため、金融機関との連携は慎重に進めてください。
参照元:司法書士法人さくら事務所
相続人間での話し合い
相続した空き家を解体する場合、複数の相続人が関係しているケースでは、全員の合意が必要不可欠です。
たとえ相続登記が未了でも、建物の所有権が複数人に帰属することになるため、勝手に解体を進めるとトラブルの原因になります。
まずは、相続人全員で話し合いを行い、「誰が解体を行うのか」「費用をどう分担するのか」について明確にしておきましょう。
特に、地方の空き家では建物の評価が低く、解体費用の方が高額になるケースも多いため、費用負担の公平性をどう保つかがポイントになります。
誰が解体するか、費用分担を決める
費用分担については法的なルールはなく、相続人間の合意がすべてです。
一般的に、以下のような分担方法があります。
- 法定相続割合に応じた費用分担
- 利用または売却を希望する相続人が全額負担
- 特定の相続人が解体費用を負担し、その分を遺産分割で調整
話し合いの内容は、書面にまとめておくと後の誤解や争いを防ぎやすくなります。
また、解体業者に依頼する際にも「契約者が誰になるか」「支払い方法はどうするか」などを明確にしておきましょう。
また、必要に応じて司法書士や不動産会社、相続に詳しい専門家の助言を得ることも、公平な解決を図るうえで有効です。
スムーズな空き家解体を実現するためにも、相続人全員での事前調整をしっかり行いましょう。
解体業者への依頼
相続した空き家を解体する際、信頼できる解体業者の選定が最も重要なステップの一つです。
業者によって費用、作業内容、対応の丁寧さには大きな差があり、安易な選択は後悔の原因になります。
特に解体工事では、アスベストの処理、廃材の分別、道路使用許可など、専門的な手続きが多数発生します。
費用の相場だけでなく、対応力や実績、安全対策の有無など、総合的な観点で業者を比較・検討することが重要です。
依頼先を決める前にしっかりと準備し、信頼できる業者を選びましょう。

① 現地調査による見積りを必ず行う
電話やオンライン見積りだけでは正確な見積りができず、着工後に追加費用が発生するリスクがあります。
② 近隣対応の姿勢を確認しておく解体工事は騒音・振動・粉じんが発生しやすく、事前対応が考えられると近隣トラブルにつながります。見積り時に業者の対応方針を確認しておくと安心です。
③業者賠償責任保険の加入と有効な建設業許可・解体工事登録を確認する隣家や通行人への損害が発生するリスクがあります。無許可業者に依頼すると、法令やトラブル発生時に行政対応が受けられないリスクがあるため、契約前に必ず書面で確認しておきましょう。
【監修者】
解体の窓口
運営責任者・田中佑弥
業界最大級、全国2300社の優良解体業者と解体工事希望者をつなぐプラットフォームを運営。
相見積もりの取り方と選定基準
解体工事の依頼では複数業者から「相見積もり」を取り、比較検討しましょう。
見積もりは、電話やオンラインでの依頼が可能です。費用の内訳には、以下の項目が含まれます。
- 解体作業費
- 重機使用料
- 廃材処分費
- アスベスト対策費
- 養生シートの設置
業者を選定する際の基準としては、以下の点に注目するとよいでしょう。
- 見積書の明細がわかりやすく、追加費用が明記されているか
- 地元自治体の許可を持つ正式な解体業者かどうか
- 解体実績が豊富で、口コミや評判が良いか
- 廃材の分別処理やリサイクル法への対応状況
- 工事中の安全対策(近隣への配慮、保険加入の有無)
価格の安さだけに注目すると、手抜き工事や後のトラブルにつながります。
必ず契約前に説明を受け、書面で確認してから契約を締結しましょう。
空き家解体の費用については、下記の記事でも解説しています。

建物滅失登記を相続人が行う
建物の解体が完了したら、法務局に対して「建物滅失登記」の申請を行う必要があります。
相続した空き家の場合、基本的に相続人が手続きしなければなりません。登記が済んでいないと、不動産の売却や管理、固定資産税の免除手続きなどに支障が出る可能性があります。
登記は解体後1か月以内を目安に速やかに申請しましょう。
個人で申請も可能ですが、書類作成に不安がある場合は土地家屋調査士や司法書士への依頼も検討しましょう。
代表相続人が行う場合の注意点
相続人が複数いる場合は、代表者(代表相続人)が他の相続人の同意を得て手続きを進めるのが一般的です。
重要なのが、「相続人全員の意思を確認した上で手続きを進めること」です。
たとえば、代表者が単独で建物滅失登記を進めた場合、後から「勝手に進めた」としてトラブルになるケースもあり、以下のような対策が有効です。
- 相続人全員からの同意書や委任状を取得しておく
- 滅失登記に必要な「建物滅失証明書」や「相続関係書類」は全員で共有
- 相続登記が未了の場合は、登記を済ませてから滅失登記へ進む
また、申請者が相続人の中の一人であっても、登記簿に記載された名義が故人のままの場合は、まず「相続登記」を先に完了させる必要があります。
法務局での申請は平日のみの対応となるため、早めに準備を進めて必要な書類や手順を確認しておくと安心です。
弊社アルバリンクは、不動産買取業者の中では数少ない年間相談件数2万件超の上場企業で他社では買い取れない物件なども積極的に買取を行っています。 「空き家」や「事故物件」「再建築不可物件」の他に「田舎の土地」「共有持分」にも対応可能です。 社会的にも大きな信用がある会社で、無理な営業などは一切行わないので、お気軽に相談・査定依頼をご利用ください。 \(無料)東証上場企業に相談・査定/
空き家の解体手続きに関するよくある質問4選
空き家の解体には、多くの手続きや準備が必要で、初めて経験する方にとっては疑問点が多いものです。
本章では、特に多く寄せられる「滅失登記の未申請」や「相続登記が未了の状態での解体」について詳しく解説します。
滅失登記を忘れるとどうなる?
建物の滅失登記を忘れたまま放置すると、様々な不利益が発生する可能性があります。
まず、登記上は建物が「存在する」と見なされたままになるため、固定資産税が引き続き課税される点に注意が必要です。
実際には更地であっても、登記簿上に家屋情報が残っていれば、自治体の課税担当はそれを基準に税額が算出されます。
不動産の売却や相続手続きの際にも、「滅失登記がされていない」と指摘されるため注意が必要です。
買主や法務局から追加対応を求められるケースも多く、余計な手間や時間が発生します。
法律上は「建物が滅失した日から1か月以内」に申請することが義務付けられており、違反した場合は10万円以下の過料を科されることもあります。
したがって、解体が完了したら速やかに建物滅失登記を申請することが、所有者としての大切な責務と言えるでしょう。
手続きに不安がある場合は、司法書士や土地家屋調査士に依頼すると安心です。
相続未登記のまま解体は可能?
原則として、相続登記を済ませていない状態での解体工事は非常にリスクが高く、おすすめできません。
登記簿上の所有者が亡くなったままの状態であれば、工事の契約書や滅失登記の申請書に正式な「所有者名」を記載することができず、法務局で受理されないケースも多くあります。
さらに、相続人が複数存在する場合には、そのうちの一人だけが勝手に解体工事を進めると、他の相続人から損害賠償を求められるなどのトラブルに発展する可能性も。
解体費用の請求や工事後の土地利用、売却、税金の分担といった問題も含め、「名義の整理」が完了していない状態では多くの場面で不都合が生じるのです。
まずは法務局で登記事項証明書を取得し、所有者情報を確認しましょう。
登記が故人名義のままであれば、先に「相続登記」を行う必要があります。
正式な所有者としての権利義務が明確になり、解体の各種手続き(見積もり依頼、契約、滅失登記など)を円滑に進められます。
補助金・助成金の申請方法は?
空き家を解体する際に、自治体の補助金・助成金制度を活用すれば、解体費用の負担を大きく軽減できる可能性があります。
多くの市区町村では、老朽化した空き家の撤去を促進するために、費用の一部(数十万円〜100万円程度)を助成する制度を設けており、事前に情報収集しておきましょう。
参照元:千葉県|市町村が行う住宅に係る支援制度(空き家)について
申請方法は自治体によって異なりますが、共通する主な流れは以下の通りです。
- 自治体のホームページや窓口で制度の有無・内容を確認
- 解体業者から見積書を取得
- 必要書類(申請書、所有者の本人確認書類、登記事項証明書など)を準備
- 解体工事前に申請(※事前申請が必須なケースが大半)
- 審査後、交付決定通知を受け取ってから工事開始
- 工事完了後、報告書と実績書を提出し、助成金を受け取る
なかでも注意したいのは、「工事着手前に申請しなければ補助対象にならない」という点です。
解体後に申請しても助成は受けられないため、必ず事前に問い合わせを行いましょう。また、助成を受けるには「空き家の築年数」「老朽化の程度」「周辺環境への影響」など、自治体が定める要件を満たす必要があります。
制度の内容は年度ごとに更新されるケースが多いため、最新情報を自治体に確認して早めに準備しておきましょう。
空き家の補助金に関しては、下記の記事も参考にしてください。

業者に依頼したほうが安心?
解体手続きは、書類の準備や各種申請、自治体とのやり取りなど煩雑な作業が多く、初めての方にとっては大きな負担となる場合があります。
経験豊富な解体業者や土地家屋調査士、司法書士に依頼することで、安心して手続きを進めることが可能です。
解体業者の中には、補助金の申請サポートや、滅失登記に必要な書類(建物滅失証明書)の作成、自治体への申請代行など、トータルでサポートしてくれるところもあります。
依頼先を選ぶ際は、「補助金申請の実績があるか」「助成金対象の工事内容に精通しているか」といった点も確認しましょう。
また、不動産の相続登記や登記簿の確認など、専門的な部分は司法書士に任せることで、よりスムーズな対応が可能です。
手数料が発生することにはなりますが、誤った申請で助成対象外になったり、登記手続きで遅延が発生したりするリスクを避けられるのが大きなメリットです。
自身で全ての手続きを行う場合は時間と労力がかかりますが、専門家に依頼すればトラブルを回避し、確実な解体と手続きの完了を目指すことができます。
安心して解体を進めるためには、「業者選び」も成功のカギとなります。
弊社アルバリンクは、空き家などの売却しづらい物件を専門に買い取っている買取業者です。 「他社で売却を断られた」「早く管理義務から解放されたい」など物件の処分にお困りの方は、弊社にご相談いただければすぐに買取査定させていただきます。 \高額ですぐ手放したい方はこちら/
空き家の解体を検討する前にアルバリンクへ相談
空き家の解体を検討している方は、まずは不動産の買取業者に査定を依頼してみましょう。
解体せずに売却できる可能性があり、余計な費用や手間をかけずに現状のままで手放せるケースもあります。
査定を無料で行っている業者が多いため、解体前に一度、価格を確認してみるのがおすすめです。
弊社「株式会社Alba Link(アルバリンク)」は、日本全国の空き家などの売却しづらい物件を積極的に買い取っている不動産買取業者です。
築古物件や立地が良くない物件に関しても、活用ノウハウを豊富に持ち合わせているため、適正な金額をつけて買い取れます。
実際に、廃墟化した空き家の買取も過去におこなっており、フジテレビの「イット」をはじめ、多くのメディアに特集されています。

空き家などでお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
弊社スタッフが、あなたのお悩みを解決できるよう、全力でサポートさせていただきます。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/
アルバリンクついて詳しく知りたい方は、アルバリンクの評判で口コミや評判・買取実績などについて詳しく説明していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
まとめ
本記事では空き家の解体に必要な手続きについて、事前準備から解体後、相続に関わる場合までを網羅的に解説しました。
解体を検討する際には、解体工事届出やライフラインの停止、近隣住民への説明、建物滅失登記や固定資産税の手続きなど、見落としがちなポイントも押さえておきましょう。
空き家の解体手続きに関して不安がある方は、まず一歩を踏み出すことが大切です。
不明点があれば、専門家や信頼できる業者への相談を検討しましょう。
適切な手続きで空き家の管理負担を軽減し、安心した暮らしへつなげてください。
\(無料)東証上場企業に相談・査定/